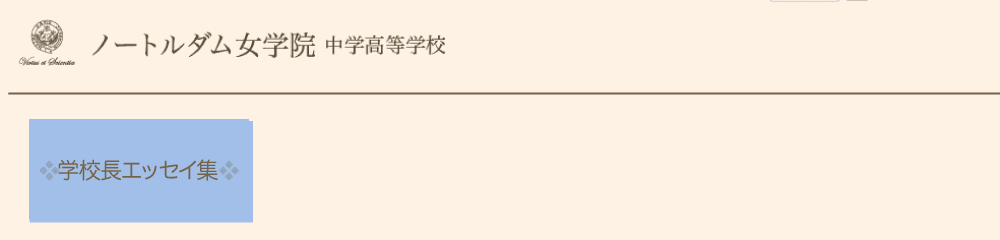昨日は、ノートルダム教育修道女会(School Sisters of Notre Dame 以下SSND)のサマープログラムの一環として、海外からのシスター方が5名、本校をご訪問され、先生方や生徒たちと交流されました。4名は米国各地から、1名はアフリカはナイジェリアからお越しになりました。5名のシスター方は、どこに生きていても、ノートルダムがキリスト・イエスの教えた生き方を貫く共同体であることを、私たちに伝えてくださっている、私はそのように感じます。
シスターポーリッサはマンケートで識字教育に携わっておられますし、シスターシンディーは現在ミルウォーキーで高齢者に関わるお仕事に、シスターテレサはメリーランドの本校の姉妹大学であるノートルダム大学でフランス語をご担当、シスタージョンはミルウォーキーの、同じく本校の姉妹大学であるマウントメリー大学の副学長です。そして、アフリカはナイジェリアからのシスターメイベルは、あちらのノートルダム女学院高校の校長先生でいらっしゃいます。ノートルダムの豊かな広がりを感じます。
朝8時15分の本校の職員朝礼でご挨拶を頂いた後、午前中本校生徒が期末考査最終日でテストに取り組む間、本校の敷地内にあるお茶室で裏千家茶道を楽しまれ、その後、修道院として6年前までシスター方の居住されていた歴史的建造物である「和中庵」をご見学。皆さん既に非常によく事前学習されていて、この建物が大正末期、1926年に建立されていることも、その中のお一人はご存じなのには驚きました。シスター方は、日本の伝統的な建造物の黒光りする廊下を静かに歩きながら、同じスピリットで生きた日本の姉妹会員たちへの、往時の暮らしに想いを馳せておられるご様子でした。ランチまでに少々時間があるので、徒歩10分のところにある法然院にお連れしました。本堂近くの方丈では、たまたま珍しく現代美術の展覧会が開催されており、この機会に私自身も普段は機会がなかった空間に入らせて頂くことができ、あの空間が放つ凛とした静寂さにシスター方と共に「京都」を感じ、感動しました。
 午後は生徒たちによる交流の集い。風呂敷の使い方のプレゼンテーション、また、この春に東北にボランティアに行った3人の生徒たちによるレポート等、力作続きの歓迎で、シスターたちからお褒めの言葉を頂きました。グループごとにシスターお一人ずつ入っていただき質問大会もしましたが、ナイジェリアのシスターメイベルのグループでは、いつの間にか皆が踊りだすなど、全員がかなりの盛り上がりを見せてくれました。
午後は生徒たちによる交流の集い。風呂敷の使い方のプレゼンテーション、また、この春に東北にボランティアに行った3人の生徒たちによるレポート等、力作続きの歓迎で、シスターたちからお褒めの言葉を頂きました。グループごとにシスターお一人ずつ入っていただき質問大会もしましたが、ナイジェリアのシスターメイベルのグループでは、いつの間にか皆が踊りだすなど、全員がかなりの盛り上がりを見せてくれました。 私にとってこの日は、ノートルダムが世界に共有するスピリットの広がりの豊かさを感じる一日となりました。生徒たちの若い日々に、世界を感じ、学び、体験することが非常に大切なことは言うまでもありません。でも、最も大切なものは、語学力でも知識でもなく、神から授けられた命を有限の存在として生きるための、生涯を貫く価値観です。これをきちんと携えて生きることは、すべてを凌駕して自分が世界のどこに生きても、人として尊ぶべきものを心から尊び、きちんと向き合って対話し、そこから生まれる共感を育み、自分の心とからだを使って行動していくことにつながります。これが、ノートルダム教育がゴールにしている大切なミッションです。今日、私たちが出会ったシスター方は、そのことを私に再認識させてくださいました。私たちの日々のノートルダム教育は、世界に通用する価値観を育む教育なのです。
私にとってこの日は、ノートルダムが世界に共有するスピリットの広がりの豊かさを感じる一日となりました。生徒たちの若い日々に、世界を感じ、学び、体験することが非常に大切なことは言うまでもありません。でも、最も大切なものは、語学力でも知識でもなく、神から授けられた命を有限の存在として生きるための、生涯を貫く価値観です。これをきちんと携えて生きることは、すべてを凌駕して自分が世界のどこに生きても、人として尊ぶべきものを心から尊び、きちんと向き合って対話し、そこから生まれる共感を育み、自分の心とからだを使って行動していくことにつながります。これが、ノートルダム教育がゴールにしている大切なミッションです。今日、私たちが出会ったシスター方は、そのことを私に再認識させてくださいました。私たちの日々のノートルダム教育は、世界に通用する価値観を育む教育なのです。
最後になりましたが、本日お出会いした5名のシスター方への感謝と、これからのお一人おひとりの使徒職に、神様の祝福が豊かにありますように心から祈っています。